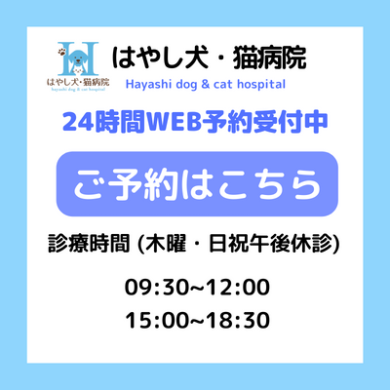犬の外耳炎の症状、治療法について解説|はやし犬猫病院

厚木市、海老名市の皆様こんにちは。
厚木市本厚木のはやし犬猫病院です。
今回は犬の外耳炎について、解説いたします。
◆犬の外耳炎は早期の治療が重要
外耳炎は犬でよくみられる疾患であり、耳道に炎症がみられ強い痒みなどの不快な症状を引き起こします。外耳炎は症状が軽い場合、治療されないことがありますが、一度進行してしまうと治りにくい特徴を持ちます。
アトピー性皮膚炎や、細菌の増殖により発症した初期の外耳炎では、刺激により細胞がよく増え、皮膚が厚くなり耳道が狭く変化していきます。狭い耳道は湿度が高く病源体が増えやすくなり耳道の環境はさらに悪化し、耳垢を分泌するアポクリン腺や、皮膚の深い部分である真皮の障害を引き起こします。これらの障害は一度外耳炎を治療しても戻ることはなく、病気が再発しやすい状態が続くようになります。外耳炎がさらに進行すると、外耳よりも身体の奥にある中耳、内耳などの聴覚や平衡感覚に重要な組織に炎症が広がるようになり、難聴や神経症状などの大きな病気を引き起こすようになります。
難治性の外耳炎や、中耳炎、内耳炎などの重い疾患を予防するために、症状が軽い外耳炎であっても動物病院を受診し、早期の治療をおこなうことは非常に重要です。
・外耳炎がよくみられる犬種
外耳炎はどのような犬でもみられる疾患ですが、コッカースパニエルやホワイトテリアなどの犬種では耳の皮膚の異常を引き起こす別の疾患が原因となり、外耳炎を引き起こすといわれています。また、甲状腺機能低下症やクッシング症候群などの内分泌疾患を持つ犬で外耳炎は起こりやすいともされています。
◆犬の外耳炎の症状
外耳炎の犬では耳の痒みや、耳垢の増加、耳の臭いなどの症状がよくみられます。痒みによって犬は耳をよく掻くようになり、頭を振る動作がみられることもあります。また、皮膚を掻き壊してしまい耳の後ろや眼の横などの脱毛や、皮膚のかさぶた、紫や黒色への変色などの症状も同様にみられる場合があります。
細菌感染を起こしている犬の耳垢は乳白色や黄色をしており、マラセチアとよばれる真菌が増殖しているときには強い臭いがする黒褐色の耳垢がみられます。ミミヒゼンダニの外耳道への寄生によるミミヒゼンダニ症では、黒い耳垢と共に非常に強い痒みが引き起こされます。
外耳炎の中には耳周りの症状だけではなく、全身症状がみられるものもあります。アトピー性皮膚炎が関係する外耳炎では、全身の痒みや脱毛、皮膚の赤み、変色などの症状がみられ、食物アレルギーが関係している場合には、口やお尻の周りに症状がみられます。また、マラセチアによる外耳炎では皮膚や被毛がべとべと変化し強い臭いを放つマラセチア性皮膚炎がみられることもあります。
◆犬の外耳炎の原因
犬の外耳炎はひとつの原因ではなく、複数の原因が発症に関係しているといわれており、アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなどの素因により悪化した耳道の環境で、病原体が増殖することで症状がみられます。外耳炎を引き起こす病源体としてはブドウ球菌やマラセチア、ミミヒゼンダニなどが知られています。ブドウ球菌やマラセチアは健康な犬の皮膚にも存在する細菌や真菌ですが、ミミヒゼンダニは外耳道に寄生する小さなダニであり、犬から犬へと感染しミミヒゼンダニ症を伝搬します。
◆犬の外耳炎の診断法
犬の外耳炎の診断は一般的に以下の手順で行われます。
①視覚的検査
耳を視覚的に観察します。赤み、腫れ、異常な分泌物、皮膚の変色などの兆候があるかどうかを確認します。また全身の皮膚にも炎症や痒みがないかも調べ、外耳炎が全身性の皮膚疾患(アレルギー性皮膚炎や脂漏症など)に関連するものか考察します。
②物理的検査
耳を軽く触って痛みの反応を確認します。また、異常な臭いがあるかどうかも確認します。
③耳道の詳細な観察:
専用の器具(耳鏡)を使って耳道を詳細に観察します。これにより、腫れ、異常な分泌物、または異物の存在を確認します。
④サンプル採取と分析
外耳炎の原因を特定するために、耳から耳垢を採取し、それを顕微鏡で分析します。これにより、細菌、酵母、寄生虫、または他の病原体が存在するかどうかを確認できます。
⑤その他の診断手段
耳の深部に問題がある場合、または外耳炎の原因がはっきりしない場合はX線撮影、CTスキャン、MRIなどの追加の診断手段が利用されることがあります。
⑥アレルギー検査
外耳炎が再発する場合や、アレルギーが原因であると疑われる場合、アレルギー検査を実施することがあります。これにより特定の食物や環境因子に対するアレルギーを判断します。
◆外耳炎の治療法
外耳炎の治療では耳道の感染に対する治療と、耳道の環境を悪化させている基礎疾患の治療を行います。
〇耳の洗浄
まず耳の洗浄を行い、過剰な耳垢や分泌物を取り除きます。これにより薬が直接感染部位に接触することが可能になり、治療効果を高めます。
〇投薬
サンプル採取と分析の結果に基づいて、適切な抗生物質や抗真菌薬を投与します。これらの薬は直接耳道に塗布する局所的なものや、飲み薬が使用される場合もあります。
〇抗炎症薬や痛み止めの使用:
外耳炎は通常、耳内の炎症を伴うため、ステロイドなどの抗炎症薬を含む薬が使用されることがあります。これにより痛みと腫れが軽減されます。明らかな痛みを示している場合には痛みを和らげるための薬が投与されることもあります。また、耳の中に投与することで約1か月持続的に感染や炎症を和らげる点耳薬もあります。

〇アレルギーの管理
アレルギーが外耳炎の原因である場合、そのアレルギーの管理が治療の一部となります。これには、特定の食物や環境因子を避ける、またはアレルギー用の薬を投与するといった手段があります。
〇外耳炎の再発防止
外耳炎の再発を防ぐために、定期的な耳の清掃や特定のライフスタイルの変更が推奨されることがあります。
〇手術
重度の外耳炎や、薬物治療に反応しない場合、手術が必要となることがあります。
外耳炎は耳掃除をおこない、耳道環境を清潔に維持することで発症を予防することができますが、頻繁の耳掃除や、過剰な耳道内への刺激によって逆に耳垢の産生を増加させてしまうことがあるといわれています。一度、かかりつけの獣医師に相談し、正しい耳掃除の方法を教えてもらうようにしてください。